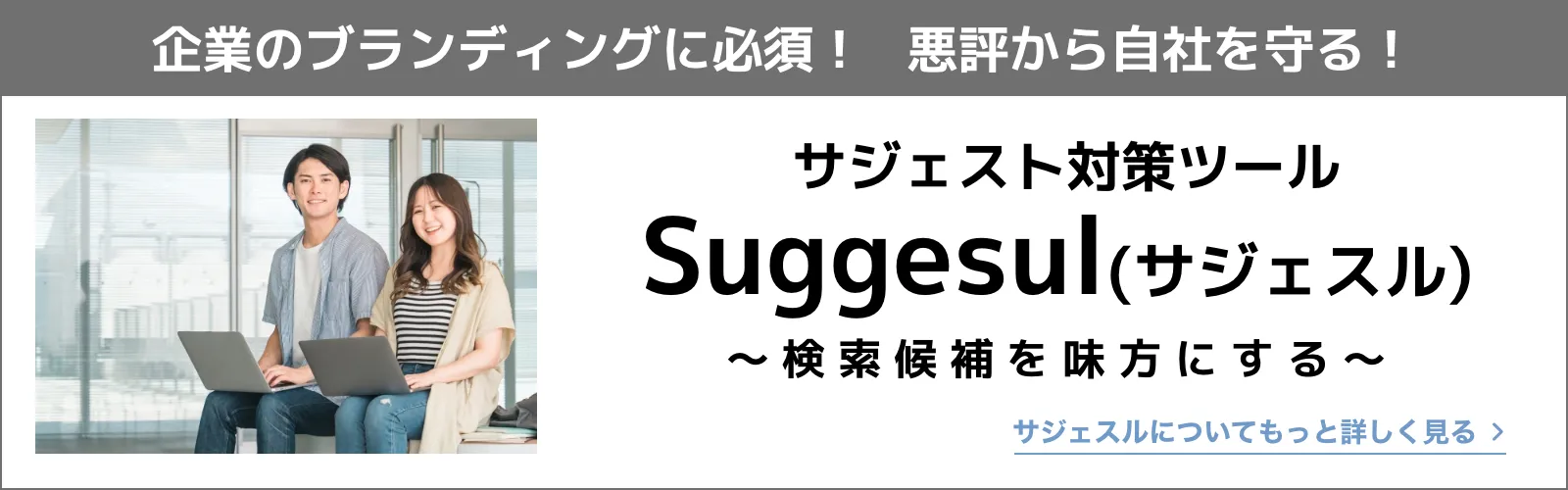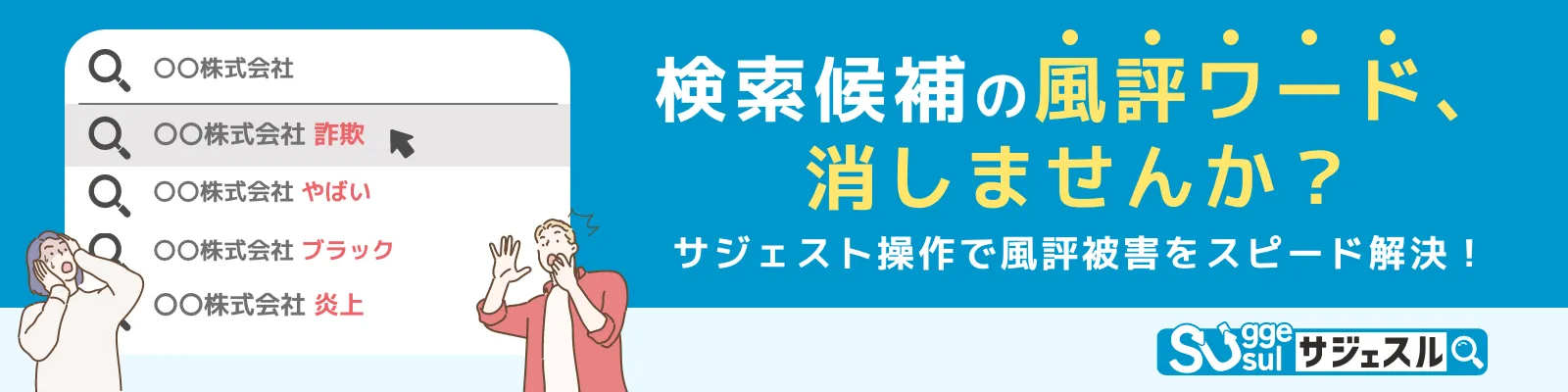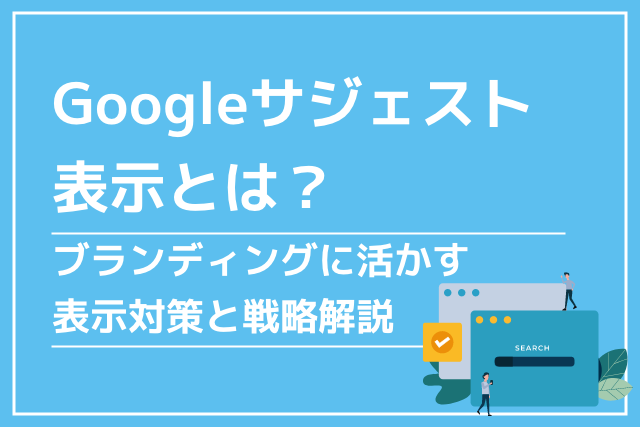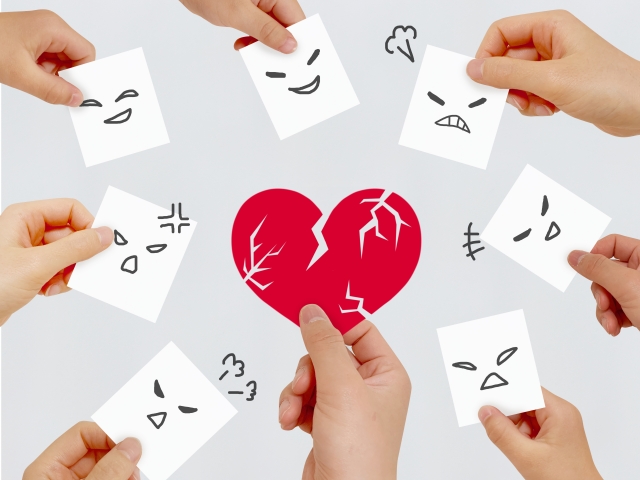インターネット上の風評被害は一度広まると個人や企業の信頼を大きく失い、放置すると深刻なダメージを与えることがあります。
悪意のある風評被害や根拠のない噂、炎上など、その影響は計り知れません。
適切な対策を講じることで、被害を最小限に抑えたり、問題を根本から解決できます。
本記事では、ネットの風評被害を未然に防ぐためのリスク対策から、万が一発生した際の初動対応、さらに根本的な解決策までを詳しく解説します。
企業や個人が今すぐ実践できる具体的な対策を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ネット風評被害でお困りの方はSuggesul(サジェスル)へのご相談をご検討ください。
ネット風評被害の種類と実例
まずは、ネット風評被害の種類と実例を紹介します。
SNSでの炎上
SNSでの炎上は、個人や企業の発言、商品・サービスに対する批判、不適切な投稿などが急速に拡散されることで発生します。
特にX(旧Twitter)やInstagram、TikTokといった拡散力の高いプラットフォームでは、一つの投稿が短時間で数万、数十万ものユーザーに届くため、その影響力は非常に大きいです。
SNSは個人で気軽に情報発信できる一方で、根拠のない噂やデマ情報が拡散されてしまうケースも少なくありません。
SNSでの炎上は、投稿者本人の意図に関係なく発生することがあり、予防や対策が難しいです。そのため、企業はSNS運用ルールを明確にし、不適切な発言を避けるための教育を徹底することが大切です。
レビューサイトや掲示板での誹謗中傷
レビューサイトや掲示板は、消費者が自由に意見を投稿できるため、誹謗中傷や根拠のない批判が広まりやすいです。
特に、飲食店や宿泊施設、ECサイトの商品レビューにおいては、虚偽の評価が投稿されることで売上に直接影響を及ぼすケースも少なくありません。
実際に、ある飲食店が競合他社の関係者によって低評価のレビューを大量に投稿され、集客が大幅に減少したケースがあります。このような誹謗中傷は、企業の信頼性を損なうだけでなく、経済的な損失にもつながるため、早急な対策が必要です。
検索エンジンのサジェスト汚染
検索エンジンのサジェスト汚染とは、検索エンジンに企業名とともに「倒産」「詐欺」「ブラック企業」など、ネガティブなキーワードが表示されることです。
サジェストが汚染されると企業のイメージが大きく損なわれる可能性があります。
このサジェスト汚染は放置するとさらに悪化し、企業に対する誤解を助長する恐れもあります。
実際に、ある企業が過去の経営問題を指摘する検索結果が長期間表示され続け、新規顧客の獲得に大きな支障をきたしたケースがありました。
対策として、ポジティブな情報を積極的に発信して検索結果の改善や定期的なモニタリングなどが効果的です。
ネット風評被害が企業に与える影響
ネット風評被害が企業に与える影響はかなり大きいです。
ここでは、ネット風評被害が与える影響について、4つの観点から解説します。
売上が減少する
ネット風評被害が発生すると、売上減少など経済的な損失が増えてしまいます。
なぜなら、風評被害によって企業の評判が低下し、消費者の購買意欲が低下するからです。
検索結果や口コミサイトでネガティブな情報が拡散されると、新規顧客の獲得も難しくなります。
さらに、風評が原因で株価が暴落し、投資家の信頼を失うケースも少なくありません。
このように、ネット風評被害は、企業の経済活動全体に大きな影響を及ぼす可能性があります。
取引先からの信頼を失う
ネット上で悪評が広がると、取引先もその影響を懸念して契約の見直しや取引の停止を検討する場合があります。
特に金融機関や投資家がリスクを避けるため、資金調達が難しくなるケースも多く、企業の成長に大きな障害となります。
実際に、風評被害によって業務提携が打ち切られ、経営が悪化した企業も存在します。
企業の信用は一度損なわれると回復が困難なため、早期の対策が必要です。
優秀な人材の採用が難しくなる
企業の評判が悪化すると、採用活動にも悪影響を及ぼします。
求職者は企業の評判を事前に確認し、風評被害によって応募を避ける可能性があるからです。
また、既存の従業員も不安を抱え、離職率が上昇するリスクもあります。
結果的に企業は優秀な人材を確保しにくくなり、採用コストの増加や業務の渋滞を招くリスクが高まってしまうのです。
社内がネガティブな雰囲気になる
企業がネット風評被害を受けると、社内の空気も悪くなります。
従業員は会社の評判悪化に不安を感じ、モチベーションの低下や生産性の低下につながることもあります。
特に風評被害が長期化すると、職場の雰囲気が悪化し、チームワークにも悪影響を及ぼします。
組織全体のパフォーマンスを維持するためにも、迅速な対応が不可欠です。
【初動で決まる】風評被害発生時の対応策
万が一、風評被害が発生した場合は初期対応が大切です。
ここでは、風評被害発生時の対応策を5つ紹介します。
いち早く察知するためのモニタリング体制
風評被害を最小限に抑えるためには、いち早く問題を察知することが重要です。
SNSや検索エンジン、口コミサイトを24時間監視するモニタリングツールを活用すると、被害の拡大を防ぐことができます。
モニタリングツールやSNS監視ツールを導入することで、悪評の拡散をリアルタイムで把握し、迅速な対応が可能になります。
風評被害の事実確認と情報収集
風評被害が発生した際は、まず情報の真偽を確認し、拡大の経路を特定しましょう。
SNSや掲示板、ニュースサイトなどを調査し、影響の範囲を把握します。
誤情報があれば速やかに訂正を求めることが大切です。
一方で、事実であれば適切な対策を講じる必要があります。冷静な情報分析や被害拡大を防ぐことが大切です。
迅速に公式発表をおこなう
風評被害への対応で重要なのは、迅速で透明性の高い公式を行うことです。
企業側が沈黙すると、さらなる憶測や誤情報が広がる可能性があります。
事実関係を正確に把握した上で、適切なタイミングで声明を発表し、誤解を解くことが求められます。
過去には、対応の遅れが更なる炎上を招いた事例もあり、迅速な情報発信が信頼回復につながります。
信頼回復と再発防止の具体策
風評被害の影響を最小限に抑えるためには、原因を究明し、再発防止策が欠かせません。
社内の管理体制を見直し、危機管理マニュアルを策定することで、同様の問題が再発するリスクを軽減できます。
また、顧客や取引先への誠実な対応を続けることで、時間をかけて信頼を回復することが可能です。
あえて静観する方が良いケースも
全ての風評被害に即座に対応するのが最善とは限りません。
小さな噂や誤った情報に過剰に反応すると、かえって話題になり、逆効果になることもあります。
実際に、静観することで風評が自然に収まり、大きな影響を受けずに済んだ事例もあります。
対応するべきか静観するべきかの判断を的確に行うことが、風評対策の成功につながるでしょう。
風評被害対策1.炎上・誹謗中傷
企業がSNSや口コミサイトなどで炎上したい場合、迅速かつ適切な対応が求められます。
特に誹謗中傷や事実無根の情報が拡散されると、ブランドイメージの低下や売上減少につながる可能性があるため、以下の対策を講じましょう。
プラットフォームへの削除依頼
SNSや掲示板、口コミサイトなどで悪質な誹謗中傷が行われた場合、該当プラットフォームのガイドラインに基づいて、投稿の削除を依頼しましょう。
サイトの運営者にお問合せフォームから削除依頼するのが一般的ですが、Google等の検索エンジンに対して削除依頼する方法もあります。
削除依頼の対象になるのは誹謗中傷や名誉毀損などに該当する場合です。
削除申請が認められるかどうかはプラットフォームの判断によるため、事前の証拠を保存しておくことが大切です。
発信者への法的措置
削除依頼で対応できない場合は、発信者に対して法的措置を検討しましょう。
具体的には次のような措置があります。
- 発信者情報開示請求
- 名誉毀損・業務妨害で訴訟
- 刑事告訴
特に企業イメージを著しく損なう投稿が続く場合は、弁護士と相談しながら法的措置を進めることが有効です。
ただし、法的措置はコストや時間がかかる点には注意しなければいけません。
風評被害対策2.サジェスト・関連キーワード対策
検索エンジンによる「サジェスト汚染」を防ぐことは企業の信頼維持に欠かせません。
サジェスト汚染は企業の信頼性やブランドイメージに悪影響を与えます。
この対策として、ポジティブなキーワードを増やすこととネガティブなキーワードを非表示にすることが有効です。
ポジティブなキーワードを増やす
ネガティブなキーワードを押し下げるためには、企業に関するポジティブな情報を増やすのが有効です。
具体的には次のような施策を実施することで、より良い検索結果にできます。
- 公式サイトでの情報発信
- SEO対策を強化した記事の作成
- プレスリリースの活用
これらの施策を継続的に行うことで、ポジティブな情報が検索結果の上位に表示され、ネガティブなワードの影響を軽減できるでしょう。
ネガティブなキーワードを非表示にする
サジェストや関連検索に表示されるネガティブなワードを削除または抑制するためには、以下の方法が効果的です。
- サジェスト対策サービスの利用
- 検索エンジンの削除依頼
- 逆SEO対策
サジェストや関連検索ワードの対策には時間がかかるため、早めに取り組むことが重要です。
また、自社での対応が難しい場合は、風評被害対策を専門とする業者に依頼するのもおすすめです。
風評被害対策3.口コミ・MEO対策
Googleビジネスプロフィールや口コミサイトでの評価は、企業のイメージを左右します。
誤解や悪意のある口コミによって風評被害が発生するのを防ぐため、適切な対策を行いましょう。
Googleビジネスプロフィールの最適化
Googleビジネスプロフィールを最適化することで、検索結果やGoogleマップ上での利便性が向上し、集客や評判管理に役立てることができます。
また、風評被害対策としても有効で、正しい情報を発信し、ポジティブな評価を増やすことでネガティブな口コミの影響を抑えられます。
Googleビジネスプロフィールの最適化の主なやり方は以下のとおりです。
- 基本情報を正確に入力する
- 写真や動画を充実させる
- 口コミを増やして適切に返信する
- 投稿機能を活用する
- よくある質問を活用する
簡単にできる対策ばかりなので、積極的に行いましょう。
優良な口コミを獲得する
優良な口コミを獲得することで、悪い口コミの影響を相対的に小さくして、悪意のある投稿を抑える効果が期待できます。
ただし、不正な方法で優良な口コミを増やすことはできないので、継続的に質の高いサービスを提供し続けることが大切です。
また、一度口コミが投稿されることで他のユーザーも気軽に投稿しやすくなります。
その結果、口コミを投稿するのをためらっていたユーザーも積極的に投稿するようになり、さらに口コミを参考に新規顧客が増えるという好循環が生まれやすいです。
風評被害対策4.逆SEO対策
逆SEOとは、検索結果の上位に表示されたネガティブ記事を下位に押し下げるための施策です。
検索エンジンの仕組みを利用して、ポジティブな情報を上位表示させることで、ネガティブな情報の露出を抑えるといった仕組みです。
自社サイトのSEO強化
企業の公式サイトが検索結果の上位に表示されることで、ネガティブな記事の影響を受けづらくなります。
具体的には次のような対策を行います。
- 企業の公式サイトのコンテンツを充実させる
- 高品質な被リンクを獲得する
これらの対策を実施することで、自社サイトの情報が検索上位に表示され、ネガティブな情報が目立たなくなるでしょう。
オウンドメディア・SNSを活用
オウンドメディアやSNSも積極的に活用しましょう。
プレスリリースなどで信頼性の高い情報を発信することで、企業のブランドイメージを高めることができます。
また、X(旧Twitter)やInstagram、TickTokなどのSNSを使うことで、逆SEOでも効果的です。
これらの対策を継続的に行うことで、企業のポジティブな情報が検索エンジンに評価されやすくなり、風評被害の影響を最小限に抑えることができます。
ネット風評被害のリスク回避術
インターネット上での風評被害は、企業のブランド価値や信用を大きく損なう可能性があります。
事前に適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑えることができます。
ここでは、ネット風評被害のリスク回避術を3つ紹介します。
情報発信戦略とリスク管理体制の構築
企業が誤解を招かない正確な情報を発信することは、風評被害を防ぐ上で欠かせません。
万が一トラブルが発生しても隠蔽せず、公式サイトやSNSを活用して、透明性の高い情報を発信することで、誤った情報が広がるリスクを軽減できます。
また、緊急時の対応フローを定めたリスク管理マニュアルを作成し、社内で共有することも大切です。
迅速かつ適切な対応ができるように、リスク管理体制を整えておきましょう。
従業員向けSNSガイドライン策定
従業員の不適切なSNS投稿が企業の評判を傷つけるケースも少なくありません。
「バイトテロ」や「機密情報の漏洩」などの問題を防ぐため、SNSの利用ガイドラインを作成し、従業員に周知することが必要です。
特に企業の機密情報や内部の事情を個人のアカウントで発信しないよう、教育を徹底することが求められます。
専門家による定期的なリスク診断
風評被害対策は一度実施すれば終わりではなく、定期的なリスク診断を行い、改善を続けることが重要です。
ネット上の企業評価や検索結果の変動をチェックし、ネガティブな情報の拡散を未然に防ぐための対応策を検討しましょう。
また、専門業者や弁護士と連携し、必要に応じて逆SEO対策や法的対応などを講じるのも有効です。
事前に対策を強化し、企業のブランド価値を守るための仕組みを整えることで、ネット風評被害のリスクを最小限に抑えることができます。
風評被害対策を依頼できる専門業者
インターネット上での風評被害は、企業や個人の信用を大きく損なうリスクがあります。
そのため、自社での対応が難しい場合は、風評被害対策の専門業者に依頼することが有効です。
ここでは、風評被害対策を依頼できる専門業者の選び方やメリットを紹介します。
風評被害対策業者の選び方と比較ポイント
風評被害対策を依頼する際には、次のポイントを比較検討しましょう。
- 対応範囲の広さ:削除依頼・逆SEO・サジェスト対策などの対応が可能か
- 実績と評判:過去の対策事例や、ユーザーからの評価が高いか
- 対応のスピード:緊急時に迅速な対応が可能か
- 透明性の高い料金体系:明確な料金プランがあり、追加費用が発生しにくいか
- 法的対応の有無:弁護士と連携し、違法な誹謗中傷に適切に対応できるか
これらのポイントを基準に、複数の業者を比較することで、最適な対策業者を選ぶことができます。
まずは、無料相談を受け付けている業者に相談してみるのがおすすめです。
信頼できる業者の特徴
風評被害対策を依頼する場合は、信頼できる業者かどうかを見極めることが大切です。
悪質な業者に依頼すると、逆に企業イメージを損ねたり、効果が期待できないリスクがあります。
信頼できる業者の特徴として、次のようなポイントが挙げられます。
- サービス内容の透明性の高さ
- 費用が明確
- 対策方法が適法
- 弁護士や法律事務所と連携している
- アフターフォローが整備されている
無料相談などを利用しながら、担当者との相性を確認しておくと契約後のトラブルを防げるでしょう。
業者に依頼するメリットと費用対効果
風評被害対策を専門業者に依頼するメリットは、迅速かつ効果的にネガティブな情報を押し下げられることです。
具体的に次のような状況では、業者の力を借りることで大きな効果が期待できます。
- 自社で対応が難しい場合
- 早急な対応が求められる場合
- 法的措置を検討する場合
費用は業者によって異なりますが、軽度の対策であれば数万円、大規模な対策が必要な場合は、数十万円程度の費用がかかることもあります。
とはいえ、ブランドイメージの損失による売上減少や信頼低下を考えれば、適切な業者に依頼することで十分な費用対効果が期待できます。
まとめ
本記事では、ネットの風評被害対策について根本的な解決策やリスク対策を解説してきました。
ネットの風評被害は企業の売上や信用に深刻な影響を及ぼします。
万が一発生した場合は、迅速な事実確認と公式発表、誹謗中傷の削除依頼、サジェスト・口コミ対策、逆SEO対策などを適切に行いましょう。
自社対応が難しい場合は専門業者に相談することをおすすめします。