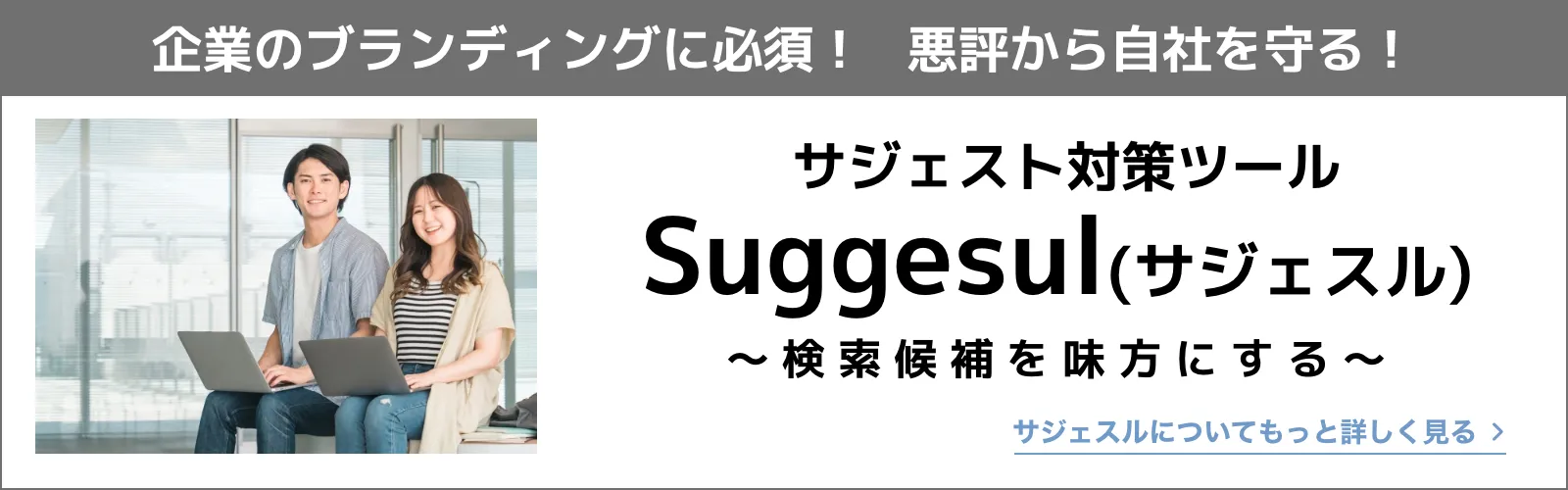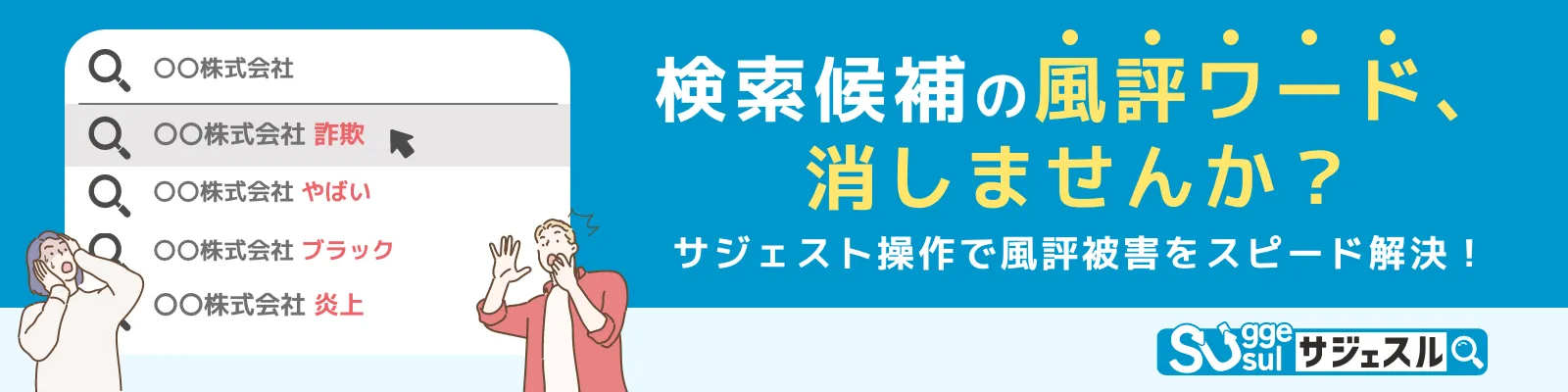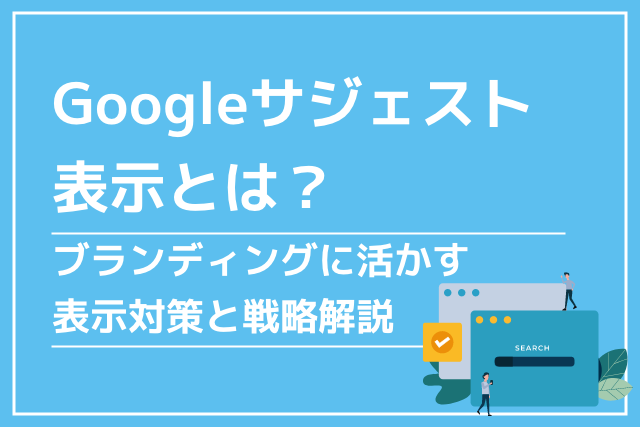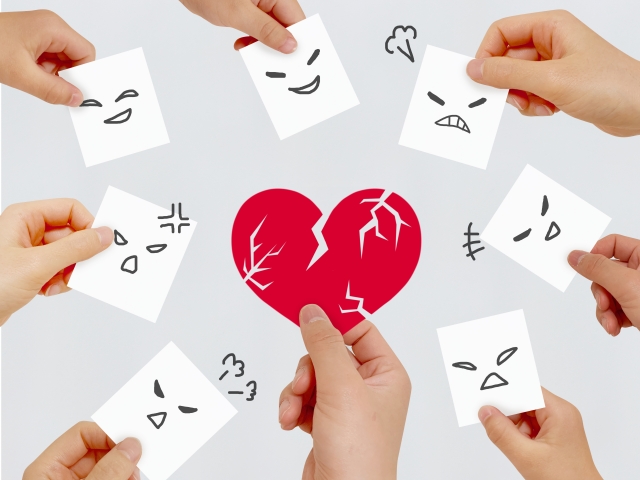現代のインターネット社会では、企業や個人に関する情報が瞬時に拡散されます。
しかし、中には誤った情報や悪意のある書き込みが含まれていることもあり、これが風評被害につながるケースが増えています。
風評被害は、企業の信頼性低下や売上減少、人材採用の妨げとなるなど、多方面に悪影響を及ぼします。
適切な風評対策を行うことで、こうしたリスクを最小限に抑え、事業の安定とブランドの信頼を守ることができます。
本記事では、ネットの風評被害の原因や対策方法、費用相場について詳しく解説します。
ネット風評対策の必要性
インターネット上で誤った情報や悪意のある書き込みが拡散されると、信頼性の低下や売上減少につながる可能性があります。
ここでは、ネット風評対策の必要性について解説します。
インターネット時代の風評リスク
インターネットは情報の拡散スピードが早く、一度拡散された情報は完全に削除することは困難です。
例えば、SNSや掲示板での悪意ある投稿が短時間で多くの目に触れ、企業の評判を大きく損なうことがあります。
さらに、検索エンジンに表示され続けることで、将来的な顧客にも悪影響を及ぼしてしまう可能性があるのです。
特に企業にとって悪い評判は一瞬で広まってしまうリスクが高いので、早期対応が重要です。
風評対策を怠ることで受ける影響
風評対策を怠ると、企業のブランドイメージが低下し、顧客離れが進む可能性があります。
また、採用活動にも悪影響を与え、有能な人材が集まりにくくなることも考えられます。
対策を怠ることによる損失には、直接的な売上減少だけでなく、人材採用の困難化、取引先からの信用低下、株価下落などさまざまです。
風評被害は時に企業存続の危機にもつながる重大なリスクなので、ネット風評対策が必要なのです。
ネットで風評被害が発生する要因
ネットで風評被害が発生する原因を3つ紹介します。
SNSや掲示板サイトでの誹謗中傷
SNSや掲示板は、誰でも簡単に意見を発信できるプラットフォームであり、誹謗中傷が発生しやすい傾向にあります。
特に、匿名での投稿が可能なプラットフォームでは、根拠のない批判や悪意のあるコメントが投稿されることが少なくありません。
たとえ企業が自社の公式SNSを持っていなくても、顧客が商品やサービスへの不満を投稿すれば、それが他の顧客によって拡散され、炎上につながるケースもあります。
このようなリスクに備えるためには、日々のモニタリングや迅速な対応が大切です。
根拠のないウワサやデマが拡散される
インターネット上では、事実とは異なる情報が拡散されることがあります。
一度広まったデマは、訂正情報を発信しても完全には消えず、長期間にわたって企業や個人に悪影響を及ぼすことがあります。
競合他社や悪意のあるユーザーが意図的に誤情報を流すケースも少なくありません。
デマの拡散を防ぐためにも、公式サイトやSNSを活用し、正確な情報を迅速に発信することが重要です。
従業員(元従業員)による内部告発
企業の内部事情を知る従業員や元従業員による告発が、ネット上で広まる可能性もあります。
中には、事実に基づくものもありますが、個人的な不満や誤解が原因であることも少なくありません。
このような情報が拡散されると、企業の信用が低下し、取引先や顧客からの信頼を失う可能性があります。
特に従業員(元従業員)の告発となると、情報を信用する人が多くなってしまいます。
対策としては、従業員との円滑なコミュニケーションを心掛けることが大切です。
また、適切な労務管理を行うことで、不満の解消やトラブルの未然防止につながります。
ネットで風評被害が発生した場合の対策
ここでは、ネットで風評被害が発生した場合の対策方法を4つ紹介します。
迅速に事実確認を行う
風評被害が発生した際には、まず事実確認を行うことが最優先です。
問題となる投稿や記事を確認し、それが事実に基づいた情報なのか、あるいは誤解や虚偽なのかを判断します。
その際、必ず投稿や記事をスクリーンショットなどして保存しておくことが大切です。
証拠を保存しておけば、投稿・記事がたとえ削除されたとしても証拠として利用できるからです。
問題の投稿やコメントが削除されてしまう前に、必ず証拠を保存しておきましょう。
関係各所と連携をとる
企業内部だけでなく、法務担当や専門業者と連携を取ることで、より効果的な対応が可能になります。
理解と協力を得ることができれば、損失を最小限に抑えることも可能です。
特に、風評被害が大規模に拡散している場合は、広報担当や弁護士と協力しながら、適切な対処を進めることが重要です。
各部門の役割を明確にした危機管理マニュアルの作成も有効でしょう。
謝罪会見や声明文を発表する
事実確認が済んだら、自社の落ち度の有無に関わらず、声明文を発信しましょう。
企業側に落ち度がある場合は、誠実な謝罪と説明が求められます。謝罪会見や声明文を発表することで、信頼回復につなげることができます。
ただし、言葉選びを誤ると火に油を注ぐ結果になるため、慎重な対応が必要です。
声明文を出す場所としては、自社サイトやSNSアカウント、ニュースサイトなどがあります。
より多くの人の目に触れるように、複数の場所に掲載するのが望ましいでしょう。
法的措置を検討する
悪質な誹謗中傷やデマに対しては、法的措置を検討しましょう。
名誉毀損や業務妨害に該当する場合、弁護士と相談しながら適切な法的手続きを進めることで、拡散を抑える効果が期待できます。
まず、SNSや匿名掲示板などでの書き込みを投稿した人物のIPアドレス開示を請求し、得られたIPアドレスなどから投稿者を特定します。
拡散を抑える効果は期待できますが、法的措置をする場合、コストと時間がかかる点には注意しましょう。
自社でできるネットの風評対策
ここでは、自社でできるネットの風評対策を3つ紹介します。
定期的なネットモニタリング
自社や業界に関する情報を常に監視する体制構築が予防対策の基本となります。
問題が小さいうちに対処することで、大規模な危機に発展するリスクを低減できるからです。
す検索エンジンやSNS、レビューサイト、掲示板などを定期的にチェックする担当者を決め、モニタリングツールの導入も検討しましょう。
特に検索エンジンでの自社名や商品名の検索結果、関連キーワードの変化に注意を払うことが重要です。
異常を発見した際の報告ルートや判断基準をあらかじめ定めておくことで、迅速な初期対応が可能になります。
従業員の教育
研修などを行い、従業員を教育することも大切です。
一人の従業員の不適切な発言や行動が企業全体の評判を傷づける可能性があるからです。
従業員にソーシャルメディアポリシーの研修を実施し、プライベートアカウントでの投稿についても注意喚起することで、風評リスクを軽減できます。
また、万が一問題を発見した際の報告ルートを明確にし、社内での情報共有体制を整えておくことも大切です。
ステークホルダーとの関係性を強化する
顧客や取引先、地域社会など関係者との良好な関係は風葉被害の抑止力になります。
信頼関係があれば、一時的な風評に対して寛容な見方をしてもらえる可能性が高まるからです。
常日頃から地域貢献活動を行っていた企業が、不祥事の際も地域住民から温かい支援を受け、早期の信頼回復につながった事例があります。
特にメディアとの良好な関係構築は、危機発生時の公平な報道につながる可能性があります。
風評対策にかかる費用
ここでは、風評対策にかかる費用について紹介します。
自社対策と外部委託の費用比較
風評対策は社内で行うものと外部委託を組みわせることが大切です。
自社で対策を行う場合は、人件費やツールの導入費のみで済みます。
すでに風評対策に関する知識やノウハウがある社員がいる場合は、費用はかなり抑えられます。
一方、外部委託する場合は、コンサルティング費用や対策費用などがかかります。
例えば、口コミ投稿や記事の削除申請は1件あたり5〜20万円が相場です。
コンサルティングを依頼する場合は月額5〜30万円がかかります。
また、外部委託の場合は月額固定費用や成功報酬型など様々な料金体系があることを理解しておきましょう。
対策内容別の費用相場
風評対策にかかる費用は以下のとおりです。
| 対策内容 | 費用 |
| 口コミ投稿や記事の削除申請 | 1件5〜20万円 |
| 逆SEO対策 | 月額5〜30万円 |
| 投稿者のIPアドレス開示請求 | 1件5〜15万円 |
| 損害賠償請求 | 着手金20万円 + 成功報酬 |
| 口コミやサジェストのモニタリング | 月額1〜30万円 |
対策内容によって費用が大きく異なるので、予算と合わせて検討しましょう。
費用対効果を高めるポイント
風評対策を行う場合、限られた予算で最大の効果を選ぶための工夫が重要です。
まずは、自社の風評リスクを考え、優先順位をつけた対策実施を行います。
全ての対策を同時に行うのではなく、リスクの高い領域から段階的に取り組むことが大切です。
無料ツールの活用や社内研修の充実など、低コストで効果的な対策から始めることも有効です。
定期的に対策の効果を測定し、PDCAサイクルを回すことで、継続的な改善と予算の最適化を図りましょう。
サジェスト対策もひとつの手段
風評対策にはいくつかの方法がありますが、サジェスト対策も効果的です。
ここでは、サジェスト対策のメリットや注意点、費用相場について解説します。
サジェスト汚染とは
サジェスト汚染とは、検索エンジンに表示されるサジェストにネガティブなワードが表示されることです。
例えば、Googleで「A社」と企業名を検索すると「A社 ブラック」「A社 パワハラ」のように、予測変換でネガティブなワードが表示されることを指します。
サジェスト汚染が発生すると、自社に対するマイナスイメージがついてしまい、企業活動に悪影響を及ぼしてしまいます。
被害が拡大してしまう前に適切に対処することが重要です。
サジェスト対策のメリット
適切なサジェスト対策を行うことで、次のようなメリットがあります。
- 風評被害の予防
- 企業イメージの向上
- 顧客獲得機会の増加
新規顧客の獲得においては、検索結果が最初の信頼性判断材料となるため、サジェスト対策の効果は大きいと言えるでしょう。
ただし、対策には一定の時間がかかるため、継続的な取り組みが必要となります。
サジェスト対策の注意点
サジェスト対策は適切な方法で実施することが大切です。
なぜなら、索エンジンのガイドラインに違反する対策は逆効果となる可能性があるからです。
不適切な手法が発覚した場合、検索エンジンからのペナルティを受けるリスクがあります。
特に注意すべき点として、自動検索ツールの乱用、不自然なリンク構築、コンテンツの複製など、検索エンジンのガイドラインに反する行為があります。
また、サジェスト対策は即効性がなく、成果が出るまでに数ヶ月かかることもあるため、長期的な視点で取り組む必要があります。
サジェスト対策の費用相場
サジェスト対策の費用相場は以下の通りです。
| 対策内容 | 日額料金 | 月額固定 |
| サジェスト表示(Google) | 1,000円〜 | 25,000円〜 |
| サジェスト非表示(Google) | 1,500円〜 | 37,500円〜 |
上記の費用はあくまで相場であり、詳細は業者によって異なります。
また、費用のプランも日額や月額などさまざまです。
複数の業者で見積もりを行い、慎重に比較検討することが大切です。
安全なサジェスト対策業者の選び方
サジェスト対策を業者に依頼する際は、次のポイントを確認しましょう。
- 風評被害対策の実績があるか
- 担当者の説明や作業はわかりやすく丁寧か
- 料金体系は明確か
- 無料相談に対応しているか
特に風評被害の対策の実績があるかはしっかり確認することが大切です。
費用は高いのに全く実績がなく、成果が期待できない悪徳業者も多いです。
まずは、無料相談に対応している業者を選ぶのが望ましいでしょう。
まとめ
本記事では、ネットの風評被害の原因や対策方法、費用相場について解説してきました。
風評被害はいつどのように発生するかわからず、放置すると業績悪化やブランドイメージの低下に繋がってしまいます。
そのため、従業員の教育や日々のモニタリングが重要になります。
予算に余裕があれば風評対策の専門業者に依頼して、定期的にモニタリングしてもらうのがおすすめです。