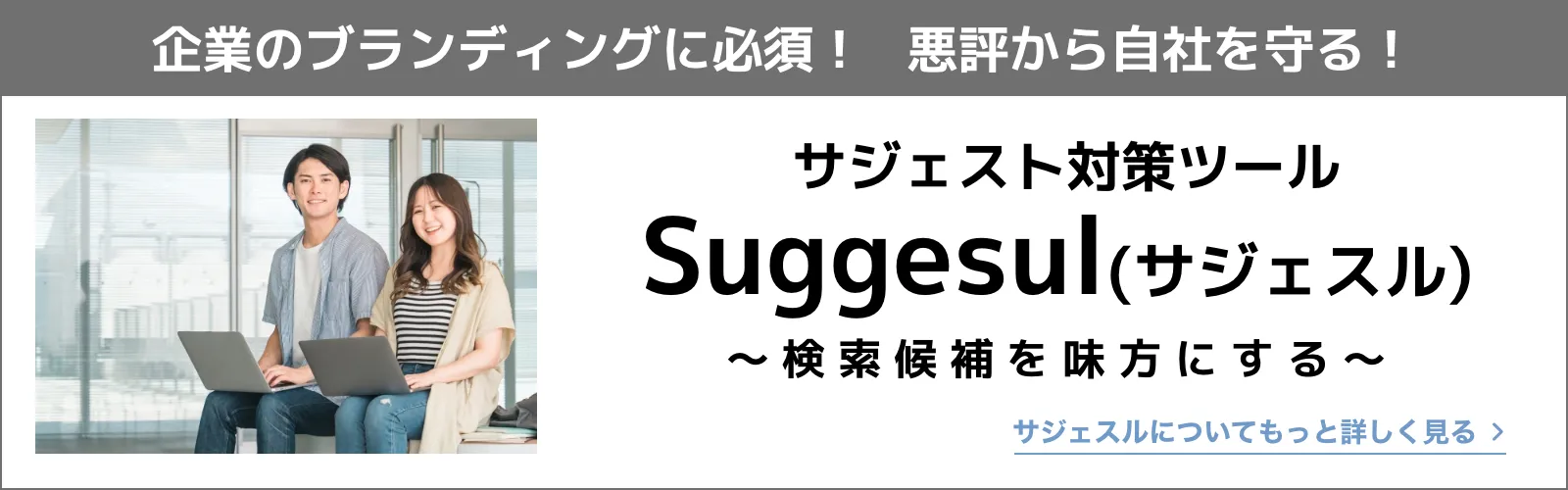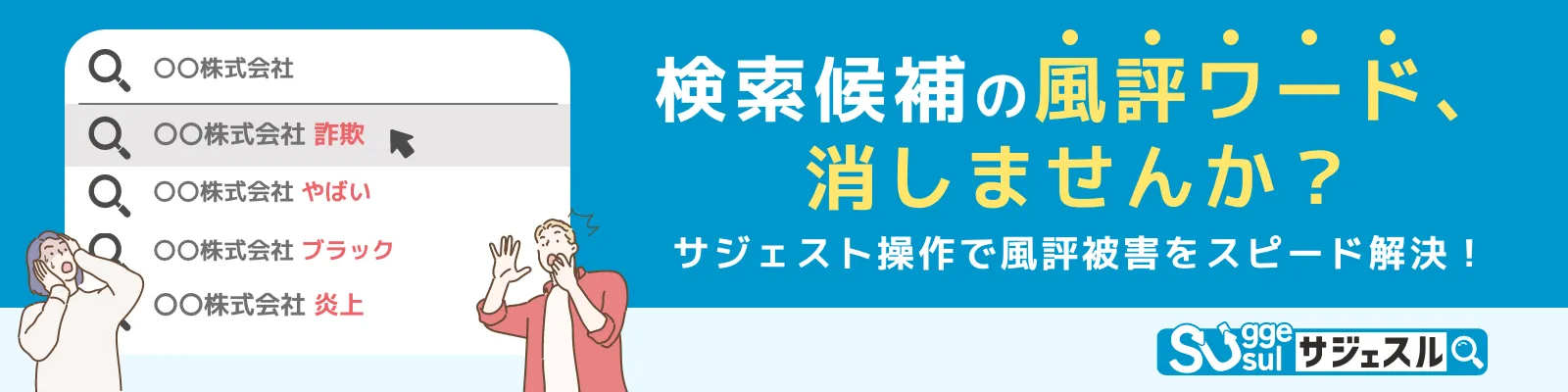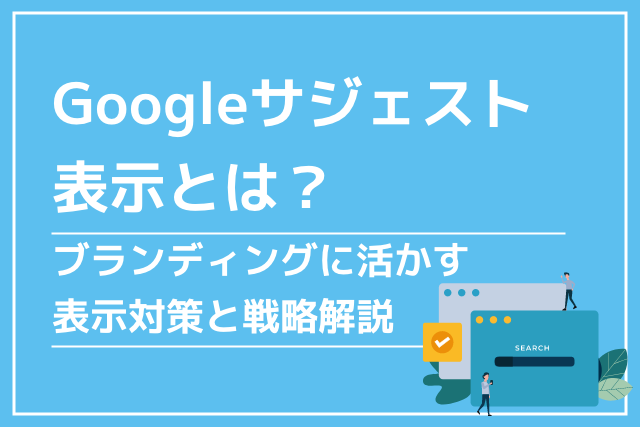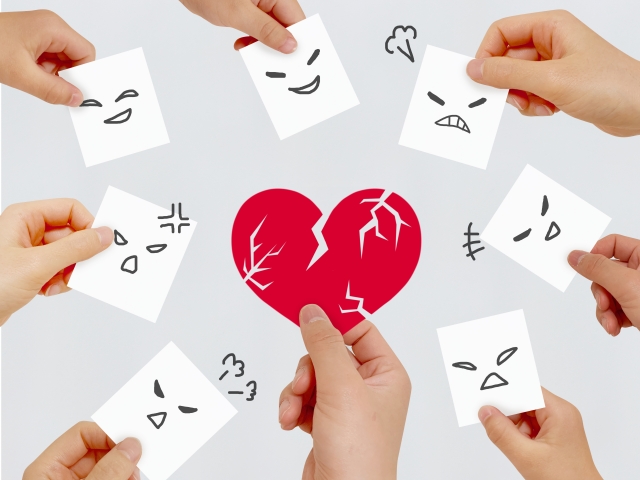「ネット上で自社に関するネガティブな情報が見つかったけどどうしたらいい?」
「同業他社で風評被害が起きているみたい、自社でも対策は必要?」
自分の会社が風評被害に合ったらどうなるのか、経営にどんな影響があるのか、不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
風評被害は、小売業、サービス業、医療業など、消費者と対面する業種だけでなく、運送業や製造業などどの業種でも起こり得ます。
たった一つの投稿が拡散され、企業のブランドイメージを大きく損なう事例に発展するケースも少なくありません。
本記事では、現代の企業が直面しやすい風評被害の事例を8つ紹介し、その影響と適切な対応策を解説します。
さらに、企業の風評被害を防ぐためのポイントや、被害に遭った際の相談先についても詳しく紹介していきます。
風評被害に遭っている、または知人が風評被害に悩まされているという方はSuggesul(サジェスル)へのご相談をご検討ください。
1.【小売業】届いたケーキが崩れていたと拡散
まずは、2023年に百貨店の高島屋で発生したクリスマスケーキが崩れていた事例を紹介します。
概要と影響
2023年のクリスマスに、有名百貨店の「高島屋」がネット販売した冷凍ケーキが、購入者のもとに崩れた状態で届いたことがSNS上で拡散され、大きな話題となりました。
特に、フリル状のクリームが特徴のショートケーキは見た目が重視される商品であったため、崩れた状態の写真が多数投稿され、企業のブランドイメージが損なわれる事態となりました。
この問題が広がるにつれ「品質管理がずさんなのでは?」「配送に問題があるのでは?」といった憶測が飛び交い、企業への批判が急増しました。
結果として、多くの購入者からの問い合わせや返品・返金の対応が必要となり、販売元は早急な対応を迫られました。
対応策
高島屋は事態を重く受け止め、次のような対応を行いました。
- 迅速な情報開示と謝罪
- 原因究明と対策の公表
- 個別の顧客対応
- 再発防止策の実施
事態が拡大した直後、企業は記者会見を行い、ケーキが崩れた状態で届いたことを認めました。
そのうえで、顧客に対して深く謝罪し、信頼回復に向けた対応策を発表しました。
このように、企業が迅速に対応し、誠実な姿勢を見せることで風評被害の拡大を抑え、最終的にはブランドイメージの回復につなげることができました。
SNSでの風評をいち早く検知するために、監視したい方は下記記事をチェックしてみて下さい。
【風評監視ツールのおすすめ8選】早期対応が企業のイメージを守る!
2.【建築業】顧客とのトラブルが拡散
続いて、ハウスメーカーで起きた顧客とのトラブルが拡散された事例を紹介します。
概要と影響
2024年1月、大手ハウスメーカー「タマホーム」がSNS上で炎上しました。
発端は、ある顧客が同社の住宅展示場を訪れた際、階段下のビスが不自然に飛び出ている様子を撮影し、SNSに投稿したことでした。
この投稿は瞬く間に拡散され、施工品質に対する疑念が広がりました。
企業側は投稿者に対しSNS投稿の削除を求める電話をかけ、その後、社員と思われる人物が投稿者の自宅を訪問し、この対応が「圧力的で不適切」と受け取られ、さらなる批判を招きました。
さらに、2月には企業が法的措置を検討すると発表し、投稿者の居住地やアカウント名を公表しています。
これが「スラップ訴訟(威圧的訴訟)」との批判を呼び、事態はさらに悪化しました。
対応策
このような事例は、企業の対応次第で風評被害を拡大させる可能性があります。
そのため、以下のような対策が必要です。
- 冷静かつ誠実な対応
- 個人情報の適切な管理
- 法的措置の慎重な判断
- 炎上の拡大を防ぐための広報戦略
最終的に、企業と投稿者の間で和解が成立しましたが、この騒動を通じて企業のリスク管理や顧客対応のあり方に厳しい視線が向けられる結果となりました。
3.【医療業】スタッフの不適切な対応への不満
近年、SNSや口コミサイトの普及により、企業のスタッフによる不適切な対応が瞬く間に拡散し、企業の評判に大きな影響を与えるケースが増えています。
概要と影響
具体的な事例として、病院施設への不満がある場合、直接病院スタッフにぶつけるのではなく、ネット上の口コミサイトやSNSに不満を書き込むケースがあります。
病院利用者は具合が悪い状態で治療を目的に病院を利用するため、それが叶わなかった場合、病院に感情をぶつけるのです。
その投稿内容が明らかにオーバーな表現であっても、ネガティブな内容は拡散されやすいため、病院にとって大きなダメージになります。
対応策
スタッフの不適切な対応による不評被害を防ぐためには、企業として以下の対応策を講じることが大切です。
- 社員教育や研修の強化
- 迅速な対応と謝罪
- 顧客対応マニュアルの整備
- 監視体制の強化
このような対策を講じることで、スタッフの不適切な対応による風評被害を最小限に抑えることができます。
企業の評判は一度失われると回復が難しいため、日頃から適切な対応を心がけることが重要です。
4.【食料品業】ジェンダーへの配慮を欠いた投稿
近年、ジェンダー問題に対する社会の関心が高まる中、企業の広告やSNS投稿が批判の対象となるケースが増えてきています。
概要と影響
具体的には東洋水産の「マルちゃん正麺」の公式X(旧Twitter)が投稿した4コマ漫画では、仕事帰りの母親が昼食で使われた食器を洗う描写が含まれたことで批判を呼びました。
この投稿に対して「結局ジェンダーロールから脱却できないのか」「なぜ母親が家事を担う前提なのか」といった指摘が寄せられました。
このような議論が発生すると、企業のブランドイメージが損なわれる可能性があります。
炎上が拡大すれば、商品の不買運動に発展することもあり、企業の売上や信頼に大きな影響を及ぼしかねません。
対応策
ジェンダー問題に関する風評被害を防ぐために、企業は以下の対応策を講じましょう。
- 投稿前の慎重なチェック
- 批判に対する冷静な対応
- 適切な謝罪と説明の発信
- 制作関係者の保護
- ジェンダー意識の向上
このように、企業がジェンダーに関する配慮を怠ると、炎上リスクが高まり、ブランドイメージに悪影響を与える可能性があります。
適切な対策を講じることで、消費者との信頼関係を維持し、企業の評判を守ることが重要です。
5.【運送業】内部告発による炎上
企業における内部告発は、不正や不適切な業務が明るみに出ることで、社会的な信頼を大きく損なう要因となります。
特に、コンプライアンス違反が指摘された場合、消費者や取引先からの信用を失い、業績にも大きな影響を与えることがあります。
概要と影響
具体的には、ヤマトホームコンビニエンスでは、引っ越し契約に関する過大請求が2018年に内部告発によって発覚しました。
この問題は2010年・2011年にも社員からの通報があったにもかかわらず、適切に対処されず、最終的に社会問題として大きく報道されることとなりました。
結果として、約4.8万件の契約で総額17億円以上の過大請求が確認され、企業としての信頼は大きく損なわれました。
さらに、2019年には国土交通省から事業改善命令が出され、一部の事業所では業務停止処分が科される事態に発展しました。
対応策
内部告発による炎上を防ぐためには、次のような対応策が重要です。
- 内部通報制度の強化
- 第三者機関の活用
- 通報者への保護措置の徹底
- 社内コンプライアンス意識の向上
内部告発は企業にとって大きなリスク要因となりますが、適切に対応することで未然に防ぐことも可能です。
信頼を損なわないためにも、積極的に対策を講じることが求められます。
6.【飲食サービス業】バイトテロ
近年、アルバイト従業員による不適切な行為、いわゆる「バイトテロ」が大きな社会問題になっています。
SNSの普及により、一度拡散された動画や画像は瞬く間に拡散され、企業の評判を著しく損なうことがあります。
概要と影響
具体的には、某回転寿司チェーンでは、従業員が調理場で食材を使って悪ふざけをする動画が拡散され、大炎上しました。
この問題を受けて、企業側は法的措置を取る方針を発表し、最終的に関与したアルバイト3人は書類送検される事態となりました。
この騒動の影響は大きく、同社の株価は130円も下落し、時価総額にして約27億円もの損失が発生しました。
また、消費者の信頼も大きく揺らぎ、一時的に来店者数の減少や売上低下を招くなど、企業経営にも深刻なダメージを与えました。
対応策
バイトテロによる炎上を防ぐためには、以下のような対策が有効です。
- 研修の徹底
- 監視体制の強化
- 厳格な処分と再発防止策の明確化
バイトテロは、一度発生すると企業に甚大な損害を与える可能性があります。
事前の対策を徹底し、不祥事の発生を未然に防ぐことが求められます。
7.【小売業】SNSでのハラスメントを思わせる発言
企業のSNS運用は、ブランドイメージの向上や販促活動に大きな影響を与える一方で、不適切な発言やキャンペーンによって炎上を招くリスクもあります。
特に、ハラスメントを連想させる言葉を使用すると、意図しない形で批判を浴びる可能性があります。
概要と影響
具体的に紳士服販売チェーン大手の「洋服の青山」は、2020年6月にTwitter上で「透けハラあるある」を募集するキャンペーンを実施しました。
「透けハラ」という言葉は、シャツが透けていることで周囲に不快感を与えるという意味で使用されましたが、一般には浸透していません。
そのため、「ハラスメントを煽っている」という批判を受け、炎上しました。
この炎上によって、ブランドイメージが低下し、SNS上での信用を失う結果となりました。
企業が新たな造語を使用する際には、言葉の意味や受け取られ方を慎重に考慮する必要があります。
対応策
SNSでの発言で炎上しないようにするには、次のような対策が重要です。
- 言葉の剪定を慎重に行う
- 社内チェック体制の強化
- ユーザー目線での発信を意識する
- 炎上時の迅速な対応
SNSの発信は企業のブランド力を高める重要な手段ですが、慎重な運用が求められます。
適切な言葉選びとチェック体制を整えることで、不用意な炎上を防ぐことが可能です。
8.【製造業】事実誤認の内容で炎上
近年、SNSの普及により、企業に関する情報が瞬時に拡散される時代となりました。
しかし、その情報が事実と異なる場合でも、企業のイメージや売上に深刻なダメージを与えることがあります。
概要と影響
具体的には、2024年11月4日、ある人気チョコレート菓子の包装を開けると生きた虫が混入していたという動画がSNSに投稿され、大きな注目を集めました。
この動画は急速に拡散され、一部の投稿は2000万件を超える表示数を記録しました。
しかし、投稿主の保護者が翌日になって「問題のチョコは最近購入したものではなく、保存状態の悪いまま長期間保管していたものだった」と事実誤認を認め謝罪しました。
それにもかかわらず、既に広まってしまった「チョコレートに虫が混入している」という印象は完全には消えず、「もうこの商品を買えない」といった声も相次ぎました。
このように、企業にとって事実誤認の炎上は、直接の過失がないにもかかわらずブランドイメージを大きく損なうリスクがあることを示しています。
対応策
事実誤認による炎上を最小限に抑えるためには、以下のような対策が有効です。
- 迅速かつ冷静な情報発信
- 証拠を示した透明性のある対応
- 批判の矛先を個人に向けない配慮
- 消費者との信頼関係を築く継続的な取り組み
事実誤認による炎上は、企業にとって予測不可能なリスクですが、適切な対応によって被害を最小限に抑えられます。
冷静かつ迅速な対応を心がけ、ブランドイメージを守るための戦略を持つことが求められます。
企業の風評被害事例から学ぶ対応策
企業が風評被害に直面した際、どのように対応するかによって被害の拡大を防ぐのか、それとも更なる炎上に繋がってしまうのかが決まります。
ここでは、企業の風評被害事例から学ぶ対応策を3つ紹介します。
迅速に透明性の高い公式情報を発信
風評被害が発生した際は、迅速に事実確認を行い、公式な情報を発信することが大切です。
具体的には次のような対応が求められます。
- 正確な情報の収集と社内共有
- 公式声明(SNSやプレスリリース)の発表
- 謝罪が必要な場合は誠実に対応
企業が自ら透明性のある情報を発信することで、不必要な憶測を防いで信頼を維持することができます。
信頼回復と再発防止につとめる
風評被害の影響を最小限に抑えるためには、単に謝罪するだけでなく、信頼回復のための具体的な行動を示すことが大切です。
具体的には次のような対応が効果的です。
- 具体的な再発防止策を公表する
- 顧客とのコミュニケーションを強化する
- ポジティブな情報発信を続ける
特に自社のミスや管理体制の問題が原因で炎上した場合は、再発防止を明確に示すことで、消費者の信頼を取り戻すことができます。
時には静観する方が良いケースもある
全ての風評被害に対してすぐに反応することが最善とは限りません。
場合によっては、企業に過剰に反応することでかえって事態を悪化させることもあります。
特に一部のSNSユーザー間でのみ話題になっている場合は、企業が関与しないことで自然に収まることが多いです。
また、事実無根の噂や誹謗中傷に対して企業が反論すると、話題が再熱し、拡散を助長する恐れもあるので注意が必要です。
企業の風評被害で悩んだときの相談先
企業が風評被害に直面した場合、適切な対応を取らなければブランドイメージの低下や経済的損失につながる恐れがあります。
社内対応だけでは解決が難しい場合は、外部の専門業者に相談することが有効です。
ここでは、風評被害に対する企業の具体的な相談先を紹介します。
警察や法律事務所に相談する
悪質な誹謗中傷やデマの拡散が確認された場合、警察や弁護士に相談する方法があります。
特に以下のようなケースでは、法的対応を検討しましょう。
- 事実無根の誹謗中傷が拡散されている
- デマが原因で業務に深刻な影響が出ている
- 執拗な嫌がらせや脅迫を受けている
- 個人情報が晒され、プライバシーが侵害されている
悪質な嫌がらせや脅迫行為、営業妨害に該当する場合、警察に相談できます。
また、ネット上のデマや誹謗中傷に対し、投稿の削除請求や損害賠償請求を行う場合は、弁護士に相談するとスムーズに対応できます。
サジェスト対策会社に相談する
サジェストが汚染されている場合や、悪質な記事・口コミが上位に表示される場合は、サジェスト対策会社に相談しましょう。
サジェスト対策会社は検索エンジンのアルゴリズムに精通しており、効果的な施策を提案してもらえます。
ネガティブ情報が広がる前に迅速に対策することで、被害の拡大を防ぐことができます。
また、長期的な監視体制を整え、再発防止策を講じることも可能です。
まとめ
企業にとって風評被害は、避けて通れないリスクの一つです。
しかし、適切な対応を取ることで、被害を最小限に抑えたり、場合によってはブランド価値を向上させたりすることもできます。
本記事で紹介したように、迅速で透明性の高い情報発信、信頼回復への真摯な取り組み、状況によっては静観する判断など、ケースに応じた対応が求められます。
また、万が一の事態に備え、警察や弁護士、専門のサジェスト対策会社などの相談先を把握しておくことも重要です。
適切なリスクマネジメントを行い、風評被害に強い企業体制を整えていきましょう。