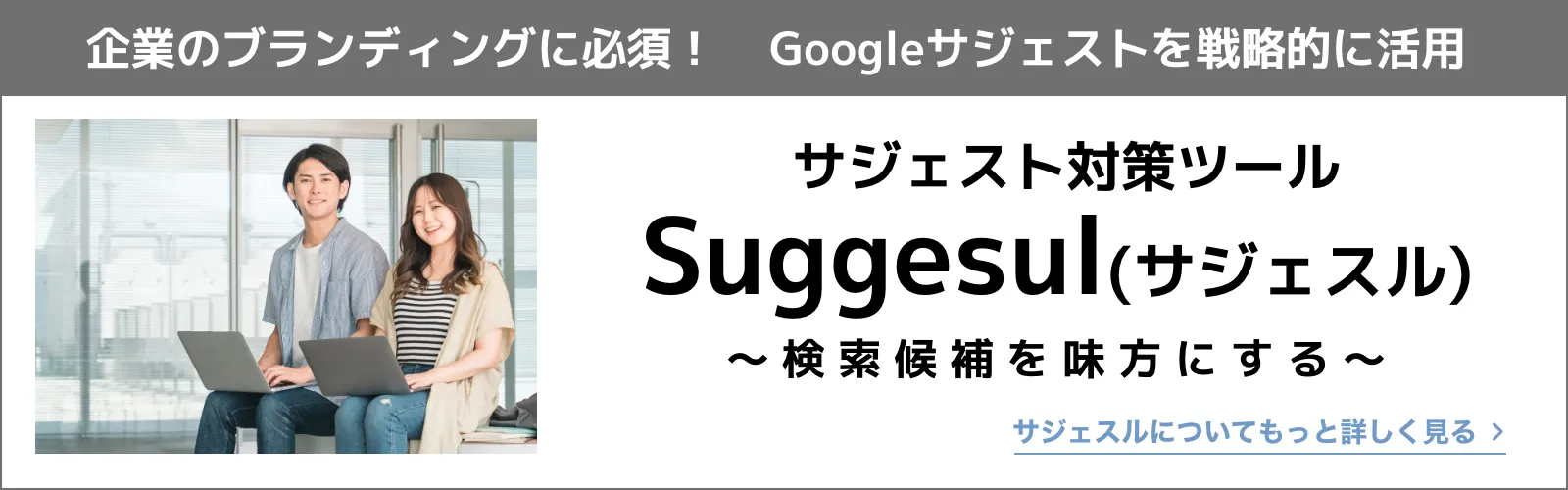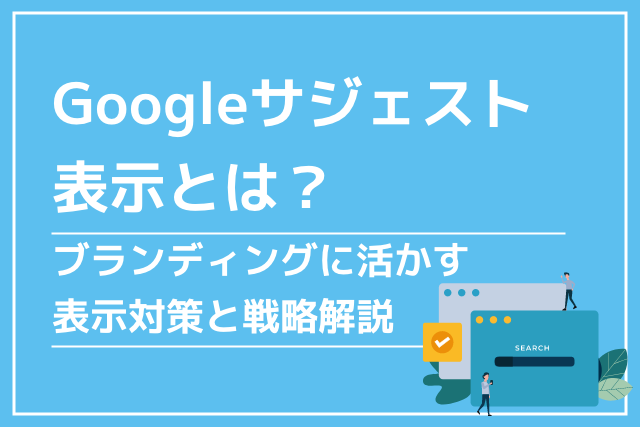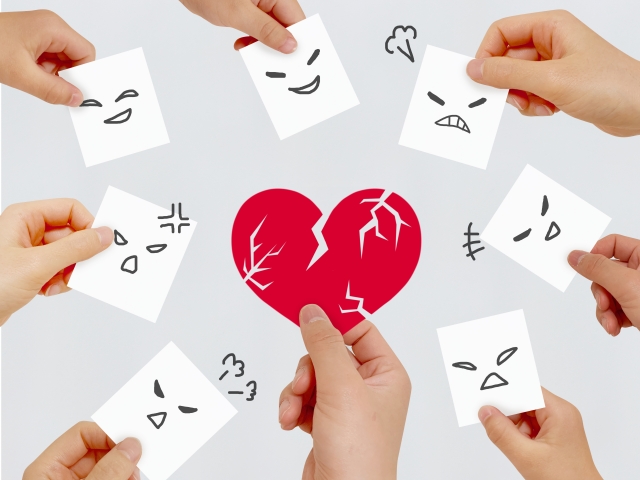Googleのサジェストに「えっ、こんなワード出るの…?」と驚くような、ひどい内容が表示されることがあります。
それが事実無根でも、検索ユーザーは真実かどうかを確かめる前にネガティブな印象を持ち、イメージが一気に悪化します。
個人でも企業でも、「信用」を一瞬で失うリスクがあるサジェスト汚染。
放置すれば、検索経由での信頼・集客に致命的なダメージが出る可能性も。
本記事では、なぜひどいサジェストが出てくるのかという仕組みから、実際に起こり得る被害、そして非表示にするための具体的な対策手順までをわかりやすく解説しています。
「このまま放っておいていいのか不安」「すぐにでも消したい」と感じている方は、今すぐチェックしてみてください。
自社のサジェストがひどい状態になっていて調査依頼をご検討の方はぜひ一度Suggesul(サジェスル)へのご相談をご検討ください。
ひどいサジェストが表示される理由
検索エンジンのサジェスト機能は、ユーザーの検索履歴や世の中のトレンドをもとに、自動的に表示される仕組みです。
便利な反面、時には「逮捕」「詐欺」「ブラック」といった悪質なワードが並ぶこともあります。
たとえ根拠のない内容でも、表示されているだけで見る人に強いマイナスイメージを与え、個人や企業の評判を大きく傷つけてしまう可能性があります。
ここでは、そうしたひどいサジェストが表示される代表的な原因を4つ、わかりやすく解説します。
SNSなどに刺激的なワードを含む投稿がある
SNS上で企業や個人に対するネガティブな発言が拡散されると、それを目にしたユーザーが興味本位で検索を行います。
特に「炎上」「やばい」「詐欺」といった刺激的なワードはクリック率が高く、結果的に検索エンジンのサジェストにも表示されやすくなります。
実際に、過激なキーワードが並ぶサジェストの例も少なくありません。
ネガティブキャンペーンを受けている
特定の人物や企業を貶めるため、意図的に悪評を流す「ネガティブキャンペーン」が行われることがあります。
これは個人の嫌がらせにとどまらず、複数人による組織的な検索・投稿によって、意図的にサジェストに悪いワードを表示させるケースも少なくありません。
例えば、競合企業やアンチグループが掲示板で連携し、特定ワードを集中的に検索することで、サジェストを操作する手法が用いられることもあります。
炎上や誹謗中傷を受けている
ネット上で炎上や誹謗中傷が発生すると、その話題は一気に拡散され、当事者に注目が集まります。
多くの人が「何があったのか?」と検索するため、サジェストにも関連するネガティブなワードが反映されやすくなるのです。
とくに大規模な炎上では、その影響が長期間続くこともあります。
過去のトラブルが再炎上している
一度ネット上に出回ったトラブル情報は、たとえ古いものであっても「デジタルタトゥー」として半永久的に残ります。
何かのきっかけで再び注目されると、再炎上が起こり、過去の問題が再度サジェストに浮上します。
再炎上によるダメージを防ぐためには、早期対応と正しい情報の発信が重要です。
ひどいサジェストが表示される仕組み
サジェストは、検索エンジンがユーザーの行動データをもとに自動生成している機能です。
ここでは、なぜひどい検索ワードがサジェストに表示されるのか、その仕組みを具体的に解説します。
過去の検索数が多いキーワードが表示される
検索サジェストは、これまでに多くのユーザーが検索したキーワードをもとに自動で表示されます。
そのため、ネガティブな話題やゴシップなど、注目を集めたワードが継続的に検索されると、サジェストにも定着しやすくなります。
一度話題になると半永久的に表示されることもあり、当事者にとっては大きな負担となるケースも多いです。
一時的な炎上・話題化により急上昇ワードが反映される
SNSや掲示板での炎上が起こると、その話題に関心を持った多くのユーザーが検索を行います。
こうした短期間の検索集中により、該当ワードが「急上昇ワード」として検索エンジンに反映され、サジェストにも表示されやすくなります。
その結果、さらに検索されるという悪循環が生まれやすく、ひどいサジェストが定着してしまうのです。
個人がひどいサジェストを放置する影響
たとえ事実無根でも、検索サジェストに悪意あるワードが並ぶことで、個人の信用や安全は大きく揺らぎます。
ここでは、個人がひどいサジェストを放置することで起こりうる具体的なリスクについて解説します。
社会的地位がおびやかされる
サジェストは、他人がその人物について調べる際の第一印象に直結します。
たとえ内容が事実無根であっても、「〇〇 詐欺」「〇〇 やばい」などのキーワードが並んでいれば、ネガティブなイメージを抱かれるのは避けられません。
就職や転職、ビジネス上の信用、さらに婚活といったプライベートな場面でも、不利益を受ける可能性があります。
たった一つの悪質なサジェストが、人生全体に影響することもあるのです。
誹謗中傷につながる可能性がある
サジェストに表示されたネガティブなワードは、SNSや掲示板などでの誹謗中傷のネタとして使われやすくなります。
ユーザーは興味本位でその人物を調べ、サジェスト内容に便乗した悪意ある投稿を拡散してしまうケースが少なくありません。
SNSは匿名性が高く、拡散力も強いため、一度広まった情報は回収が難しいです。
結果的にサジェストから始まった誤解や偏見が、炎上や名誉毀損にまで発展するリスクがあります。
個人情報が漏れる可能性がある
悪質なサジェストを放置すると、「〇〇 自宅」「〇〇 勤務先」などのワードが表示されることもあります。
これにより、ネットユーザーが本名や顔写真、住所などの個人情報を探し出し、SNSや掲示板で晒すといった被害が発生します。
中には、ストーカー被害や職場への嫌がらせにつながるケースも少なくありません。
早期対応が必須であり、風評被害対策を専門とする弁護士や専門家への相談がおすすめです。
企業がひどいサジェストを放置する影響
ひどいサジェストは企業のブランドイメージの信用を大きく損なうリスクをはらんでいます。
ここでは、企業がひどいサジェストを放置する影響について解説していきます。
サジェストの内容=企業の印象になる
ユーザーが企業名を検索する際、最初に目にするのが検索サジェストです。
そこに「ブラック」「倒産危機」「クレーム」などのネガティブなワードが並んでいると、それだけで信頼感が損なわれます。
実際には事実無根でも、初見の印象が「その企業=問題がある」と結びついてしまうため、誤解や偏見が定着しやすく、企業ブランドの信用低下につながります。
顧客や取引先に不信感を与える
検索の時点でネガティブな印象を与えてしまうと、見込み顧客や取引先は「この会社、大丈夫かな…?」と不安を感じ、自然と離れていきます。
その影響で、問い合わせの減少や新規契約の停滞、さらには既存顧客の離脱につながり、売上に直結するケースも少なくありません。
加えて、いくら広告やキャンペーンに力を入れても、検索結果で悪い印象を持たれていれば意味がなく、せっかくの予算が無駄になってしまうリスクもあります。
採用や人材確保が困難になる
求職者は企業名を検索する際にサジェストも確認する傾向があります。
そこにネガティブなワードがあれば、応募を控えるだけでなく「ブラック企業かもしれない」と悪い噂が広がりかねません。
また、現在働いている社員の指揮にも影響し、社内の雰囲気が悪化、離職率の増加につながる恐れもあります。
結果として、優秀な人材の流出と確保難という悪循環に陥ります。
ひどいサジェストの拡散が進行し収拾がつかなくなる
ひどいサジェストは放置すると、自然に拡散が進み、検索エンジンに定着してしまいます。
検索数が増えることで関連ワードとして強化され、SNSやまとめサイト、掲示板にも話題が波及する可能性があります。
一度広がった風評は削除や訂正が難しく、企業広報や法的対応が追いつかないという事態にもなりかねません。
だからこそ、早期のモニタリングと専門的な対応が不可欠です。
早急な対応がカギ!ひどいサジェストへの対策手順
ひどいサジェストは放置するとさらに拡大し、被害が深刻化してしまう恐れがあります。
ここからは、被害を最小限に抑えるために実行すべき具体的な対策手順を11ステップで解説していきます。
手順1.サジェストの内容を記録・保存する
まず最初に行うべきは、GoogleやYahoo!の検索サジェストに表示されているキーワードの証拠を保存することです。
削除申請や法的対応を行う際に、表示されていた内容を記録していなければ主張の裏付けが難しくなります。
スクリーンショットや画面録画等で、検索ワード・日付・検索エンジンの種類などを記録しておきましょう。
また、時間の経過とともに変動する場合もあるため、数日ごとに状況を保存することもおすすめです。
手順2.SNSや掲示板などを監視する
ひどいサジェストの多くは、SNSや掲示板などでの発信・拡散が火種になって広がっていきます。
特に、X(旧Twitter)や5ちゃんねるといった拡散力のあるプラットフォームでは、何気ない投稿が一気にサジェストに影響を与えることもあります。
そのため、「どの投稿が発端なのか」「誰が拡散しているのか」を特定することが重要です。
特定のアカウントが執拗に投稿していたり、掲示板でスレッドが乱立している場合は、早めの対応をしないと被害が広がり続けます。
投稿内容・発信源・拡散スピードなどを定期的にモニタリングし、必要に応じてスクリーンショットを保存して証拠を残しておくようにしましょう。
手順3.検索エンジンへ削除申請する
GoogleやYahoo!では、名誉毀損やプライバシー侵害の恐れがある場合に、検索サジェストの削除申請を受け付けています。
特に「〇〇 詐欺」「〇〇 ブラック」などのワードは、放置すると実害を伴うため、早急な削除が望まれます。
Googleでは「法的な削除に関する申立フォーム」、Yahoo!では「情報の削除に関する申請窓口」から申請可能です。
手順4.関係各署へ共有する(企業)
企業が被害を受けている場合、広報や法務、人事、経営陣など、関係部署への情報共有が欠かせません。
現場と経営層で情報が分断されていると、不適切な対応や情報漏洩につながる恐れがあります。
社内では、問題の概要・表示されているサジェストの内容・削除申請の進捗・今後の方針などを整理し、迅速に対応できる体制を構築することが大切です。
危機対応マニュアルが未整備であれば、これを機に整備することも検討しましょう。
手順5.原因となる発信を削除依頼する
ひどいサジェストの元になっている投稿や記事が特定できた場合は、投稿者や運営元に対して削除依頼しましょう。
X(旧Twitter)やInstagram、5ちゃんねるなどには削除申請用の窓口が用意されており、名誉毀損・プライバシー侵害などに該当する場合は受理されるケースもあります。
原因となる投稿を削除できれば、関連する検索行動が減り、サジェストが改善されるきっかけにもなります。
手順6.公式に声明を発表する
事実と異なる内容がサジェストに出ている場合や誤解が広がっているときは、公式サイトやSNSを通じて正しい情報を発信することが効果的です。
企業の姿勢や見解を明確にすることで、ユーザーや顧客の不安を軽減し、企業の信頼回復にもつながります。
また、公式声明を発表することで、メディアや取引先にも正確な情報を伝えることができ、デマや誤情報の拡散防止にもなります。
手順7.サジェスト対策専門会社へ依頼する
自社や個人だけで対応するのが難しい場合は、サジェスト対策を専門に行う業者へ依頼するのも有効な手段です。
専門業者は、ネガティブなワードを検索結果から目立たなくし、代わりにポジティブなキーワードを上位に表示させるような対策を行います。
検索エンジンの仕組みやアルゴリズムに精通しているため、迅速かつ的確な対応が可能です。
「一刻も早く改善したい」「社内に知見がない」といった場合には、費用対効果の高い選択肢となるでしょう。
手順8.弁護士へ相談する
サジェストの内容が極めて悪質で、業務妨害や名誉毀損に該当する可能性がある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士は法的根拠に基づいた削除請求や、投稿者への損害賠償請求などを代行してくれます。
検索エンジン側への法的な申請が通りやすくなるメリットもあります。
費用については依頼内容や弁護士によって異なりますが、まずは、無料相談に対応している弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
手順9.ポジティブなコンテンツを発信する
ネガティブなサジェストは、ポジティブな検索行動によって上書きすることができます。
例えば、「企業名 評判」「企業名 サービス」など、ポジティブな切り口で記事を作成することで、検索エンジン側の評価が変化し、ネガティブワードの表示頻度が下がることがあります。
特に企業ブログやSNSを積極的に活用し、継続的な発信を行うことが大切です。
手順10.サイトを見直す
自社サイトの内容が古い、ユーザー目線で作られていないといった場合、検索エンジンからの評価が低下し、ネガティブな情報に埋もれやすいです。
検索されやすい疑問に対応したページを増やしたり、専門的なコンテンツを増やしたりすることで、ポジティブな検索結果が上位表示されやすくなります。
SEOの観点からも、コンテンツの質と量を見直すことはサジェスト対策に有効です。
手順11.再発防止策をとる
一時的にサジェストを改善できたとしても、同様の被害が再び起こる可能性があります。
そこで、再発防止に向けた体制作りが欠かせません。
具体的には、SNSやネット投稿を監視するツールの導入、社員への情報発信リテラシー教育、社内での対応ルールの策定などが挙げられます。
まとめ
検索サジェストに表示されるひどいワードは、必ずしも事実に基づいたものとは限りません。
それでも多くの人が目にすることで、企業や個人に対する印象は大きく左右されてしまいます。
放置すれば、社会的信用の低下や誹謗中傷の拡大といった深刻な事態を招く可能性もあります。
被害を最小限に抑えるためにも、日頃からネット上の評判を監視し、いざというときには専門業者や弁護士と連携しながら迅速に対応することが大切です。