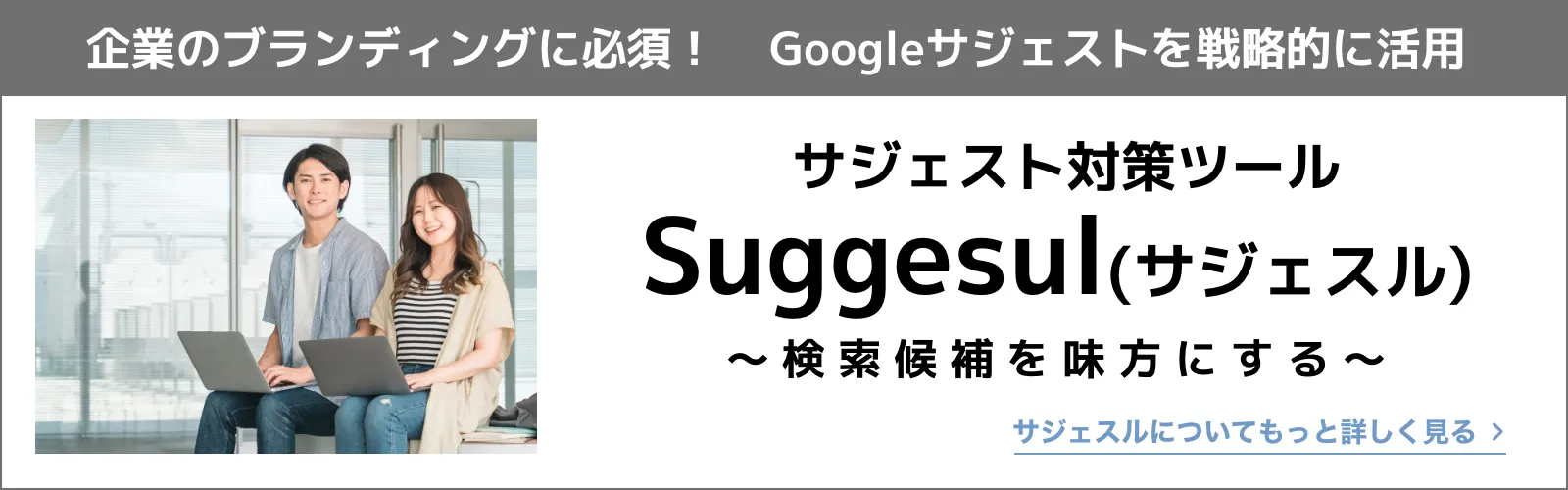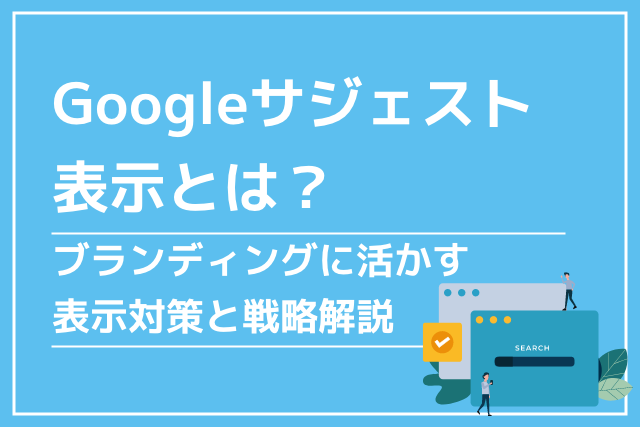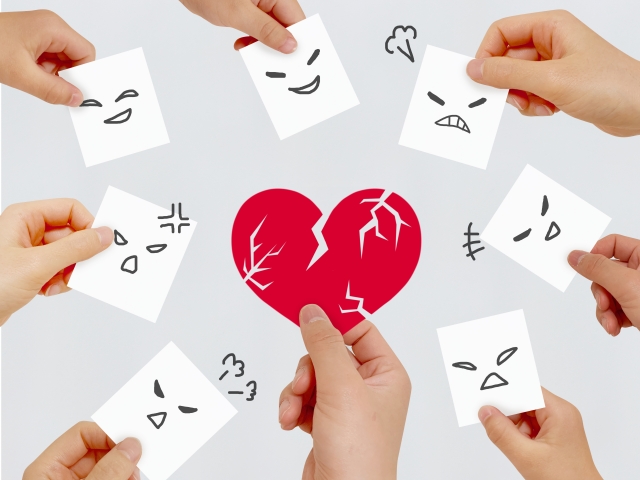ネット上では個人・法人含めて、誹謗中傷行為がよく見られます。
誹謗中傷されてしまった場合、風評被害を広げないためにも早めの対策が必要です。
早めに対策すれば誹謗中傷の被害を最小限に抑えることができます。
本記事では、ネット誹謗中傷に対する初期対応から法的措置、メンタルケアの方法まで詳しく解説します。
ネット誹謗中傷対策でお困りの方はSuggesul(サジェスル)へのご相談をご検討ください。
ネットでおきた誹謗中傷の最新事例
まずは、ネットで起きた誹謗中傷の最新事例を紹介します。
企業の口コミサイトに事実無根の書き込み
まずは、「転職会議」という企業の口コミサイトに事実無根の書き込みをされた事例です。
具体的には「〇〇会社にはボーナスがない」「〇〇会社が詐欺的な営業をしている」という口コミ情報が掲載されました。
しかし、同会社はボーナスを支給していましたし、詐欺的な営業をしている事実もありませんでした。
つまり、口コミは事実無根であり、単に〇〇会社の評判を下げるだけの誹謗中傷です。
事実無根の口コミは企業イメージに深刻なダメージを与えます。
「転職会議」は就職の際に参考にされる有名なサイトであり、口コミを放置していると風評被害は拡大するため、迅速な対応が求められます。
店舗でコロナ陽性者が確認されたというデマ
コロナ禍でスーパーやコンビニなどの店舗でコロナ陽性者が確認されたというデマが拡散された事例もありました。
中には実際に陽性者が出ていたケースもあるかもしれませんが、陽性者がいなかったにも関わらず、拡散されたケースも少なくないでしょう。
デマの拡散力は非常に強く、事実確認をせずに情報が拡散されると企業にとって大きな被害を生み出します。
情報の真偽が不明であっても、念のために店舗の利用を控える行動をとる顧客も少なくないからです。
歯科医院に対する悪質な口コミ
歯科医院を経営していた医療法人に対して、誹謗中傷ともとられる悪質な口コミが書き込まれた事例がありました。
具体的には、Googleの運営する口コミサイトに次のような口コミが投稿されました。
- 公式サイトの料金よりもかなり高額
- 料金が高いのにアルバイトの医師の技術が低い
- セラミックによる治療後すぐに虫歯になった
しかし、その歯科医院の料金は他の医院と比べて高額とは言えない価格帯です。
また、セラミック治療後のクレームの医療記録もありませんでした。
医療の専門性を一般の人が正確に判断するのは難しく、感情的な書き込みが医院の評判を不当に下げることがあります。
患者側の一方的な主張が、専門家の評価を覆すケースも少なくありません。
事例からわかる誹謗中傷の共通点
誹謗中傷には明確な共通点があります。
まず、匿名性を利用した責任回避が特徴です。
実名での発言よりも過激な表現になりやすく、事実確認を怠る傾向があります。
また、一度広まった情報は完全に削除することが難しく、長期間にわたり検索結果に残り続けます。
また、誹謗中傷は感情的要素が強く、合理的な議論とはかけ離れた内容になりやすいです。
誹謗中傷は企業や個人の評判を短期間で著しく損なう可能性があり、対策の重要性が高まっています。
ネットで誹謗中傷が発生するプロセスと影響
ネット上の誹謗中傷はまず単なる批判や不満から始まります。
匿名性によって発言が過激化し、事実確認のないままSNSなどで共有され、短時間で広範囲に情報が届きます。
また、検索結果に表示されると長期的な影響が生じ、企業名や個人名の検索結果に否定的な情報が表示され続ける仕組みです。
ネットで誹謗中傷が発生すると、顧客離れや取引先からの信用低下は直接的な売上減少につながってしまいます。
また、従業員のモチベーション低下やメンタルヘルスの悪化は組織全体の生産性を下げる原因になってしまうため注意が必要です。
誹謗中傷は一時的な問題ではなく、長期にわたり組織の存続を脅かす重大な課題となります。
ネットで誹謗中傷を受けた時の対策
ここでは、ネットで誹謗中傷を受けた時の対策を7つ紹介します。
影響を最小限に抑えるための初期対応
誹謗中傷を発見したら、冷静かつ迅速な対応が必要です。
まずは誹謗中傷の内容をスクリーンショットで記録し、URL、投稿日時、投稿者情報を記録します。
投稿内容だけでなく、コメントや「いいね」の数なども含めた詳細な記録が有効です。
社内で対応チームを結成し、事実関係の確認と今後の対応方針を決定します。
感情的になるのではなく、客観的な事実に基づいた冷静な判断が重要です。
初期対応の良し悪しが、その後の展開を大きく左右する可能性があります。
プラットフォームへ削除依頼する
GoogleやYahoo!の検索結果に対する削除依頼、X(Twitter)やFacebookなどのSNS投稿、口コミサイトへの対応などがあります。
該当する投稿がプラットフォームのガイドラインのどの項目に違反するのか具体的に示し、証拠を添えて申請することで削除してもらえる可能性があります。
削除依頼は複数回行う必要があることも多く、粘り強い対応が求められます。
プラットフォーム側の判断で削除されないケースもありますが、まずは運営会社への働きかけを試みるべきです。
法的措置も検討する
名誉毀損罪や業務妨害罪に該当する可能性があるケースでは、法的な対応が効果的です。
法的措置により投稿者情報の開示請求や損害賠償請求ができます。
投稿者やサイトの管理者にIPアドレスなどに開示請求することで、投稿者やサイト運営者の特定が可能です。
法的措置は時間とコストがかかりますが、悪質な誹謗中傷に対して抑止力となります。被害の程度に応じた法的アプローチを検討することが大切です。
公的機関へ相談する
インターネット上の誹謗中傷に対しては、公的機関も相談窓口となります。
| 相談先 | 相談内容 |
| 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業) | 誹謗中傷に対してどのように対応すれば良いか分からない。 |
| インターネット人権相談(法務省) | ネット上の書き込み・画像を削除したい。 |
| 誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会) | 書き込んだ相手に損害賠償を請求したい。 |
法務省の「インターネット人権相談」や総務省の「違法・有害情報相談センター」などが主な相談先です。
相談前に被害状況を整理し、具体的な質問事項をまとめておくと効率的です。公的機関からのアドバイスを受けた上で、必要に応じて民間の専門家へ相談するという段階的なアプローチも効果的です。公的機関は強制力を持たないケースが多いものの、適切な解決方法へのガイダンスや心理的なサポートを提供してくれます。
取引先や顧客への説明
風評被害を防ぐためには、関係者への適切な説明が欠かせません。
取引先への説明会開催や顧客向けの公式声明発表などがあります。
事実関係の整理、対応状況の説明、今後の対策など具体的な情報を提供します。
過度に防衛的な姿勢ではなく、誠実な対応を心がけることが信頼回復につながります。
説明は簡潔かつ正確であるべきで、誇張や感情的な表現は避けるべきです。
関係者とのコミュニケーションを維持することで、風評被害の拡大を防ぎ、支援者を増やすことができるでしょう。
担当者に対するメンタルケア
誹謗中傷は対応する担当者の心理的負担が大きいです。
心理的ストレスが蓄積すると、判断力の低下や健康問題につながってしまいます。
そのため、万が一社内に誹謗中傷された当事者がいる場合は、カウンセリングやメンタルケアの提供が大切です。
- SNSを見ないようにする
- 社内の相談窓口を設ける
- 専門家へ相談する
誹謗中傷への対応は長期化することも多いです。
当事者を孤立させないよう、定期的な声かけや評価を行うことも効果的でしょう。
誹謗中傷対策の専門家へ相談
ネットの誹謗中傷対策に強い専門家へ相談・依頼することも効果的です。
誹謗中傷対策に特化した専門家へ相談すると、効率的かつ効果的な対応が可能になります。
専門家は定期的なモニタリングやサジェストの削除など、さまざまな対策ができます。
モニタリングやサジェスト対策などを日頃から行っておけば、大規模な炎上を未然に防ぐことも可能です。
費用対効果を考慮しつつ、専門的なアドバイスを取り入れることで、誹謗中傷問題の迅速な解決につなげることができるでしょう。
ネットの誹謗中傷を未然に防ぐ対策
ここでは、ネットの誹謗中傷を未然に防ぐ対策を4つ紹介します。
リスク管理でもしもに備える
誹謗中傷はいつどのような理由で発生するかが予測できません。
誹謗中傷が発生しないことが望ましいですが、万が一発生してしまった場合のリスク管理体制の構築が大切です。
具体的には次のような管理体制を整えておきましょう。
- SNSのガイドラインや情報発信に関するポリシーを策定する
- 誹謗中傷が発生した場合の対応を明確にしておく
- 誹謗中傷の火種にならないよう従業員への教育を行う
誹謗中傷のリスクは全ての企業や個人に存在するという認識を持ち、「起こりうる問題」として準備することが大切です。
特に広報部門と法務部門の連携体制を整えておくことで、迅速かつ適切な初動対応が可能になります。
モニタリングで早期発見
定期的なモニタリングによって問題を早期に発見することは被害を大きくしないために大切なことです。
企業名や商品名などのキーワード検索、SNSやレビューサイトの定期チェックなどがあります。
モニタリングは単なる誹謗中傷の発見だけでなく、顧客の声や市場動向の把握にも役立ちます。
継続的かつ網羅的な監視体制を構築することで、炎上の原因となる投稿を早めに消すことができるでしょう。
発生してしまったあとの再発防止策
誹謗中傷は一度だけでなく繰り返されることもあります。
再発を防止するためにも、発生原因の分析、弱点の洗い出し、対応プロセスの見直しなどが必要です。
誹謗中傷の内容や発生状況を詳細に記録し、共通点や傾向を分析しましょう。
また、社内コミュニケーションの改善や透明性の向上など、誹謗中傷の原因となりうる問題の解決にも取り組むべきです。
弁護士や専門家との連携
弁護士や、コンサルタント、Webマーケティングの専門家など、専門家との日常的な連携も大切です。
日常的な関係構築が緊急時の対応な対応を可能にします。
顧問弁護士との定期相談やネット危機管理の専門家との情報交換、セミナーへの参加などがあります。
専門家は単なる対応者ではなく、予防策の提案者としても重要です。
費用面の懸念もありますが、危機発生後の対応コストと比較すれば、必要な投資と言えるでしょう。
誹謗中傷の加害者にならないための注意点
ここでは、誹謗中傷の加害者にならないための注意点を3つ紹介します。
責任を持って発信する
情報発信には責任が伴うため、発信者としての自覚や倫理観が重要になります。
特に企業の公式アカウントなどでは、正確で透明性の高い情報を発信しましょう。
極端な発言は、ファンを獲得しやすいメリットもありますが、反感を買いやすいというリスクもあります。
SNSの気軽さに流されず、一度投稿した内容は完全には消せないという認識を持つことが大切です。
投稿前の事実確認、冷静な表現の選択、発信内容の影響範囲の予測などを心がけましょう。
法的責任・人権の意識をもつ
SNSなどの発信内容には法的責任が伴うことを理解しましょう。
表現の自由にも限界があり、他者の権利を侵害する表現は法的制裁の対象となります。
実際に誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪行為に該当する可能性が高いです。
匿名だからと過激な表現を用いて個人や企業を攻撃し、訴訟に発展するケースが増えています。
インターネット上での発言も現実社会と同様の責任が問われることを認識しましょう。
インターネットネットリテラシーを高める
誹謗中傷の加害者にならないために、インターネットリテラシーを高めましょう。
情報の真偽を見極め、適切に発信・受信する能力を養います。
具体的には、SNSでの拡散前に情報源を確認する習慣や、感情的になりそうな時は投稿を一旦保留するなどの対応があります。
インターネットの特性を理解し、デジタルコミュニケーションのマナーやルールを学ぶことは、加害者にも被害者にもならないための基本です。
『サジェスト対策』も誹謗中傷対策に有効
ネットの誹謗中傷の対策として、「サジェスト対策」も有効です。
ここでは、サジェスト対策の必要性や効果、具体的な成功事例について紹介します。
サジェスト対策の必要性
Googleなどのサジェストにネガティブなワードが表示されると深刻な問題になります。
なぜなら、多くの人が検索時にサジェストに表示される候補を選択する傾向があるからです。
「会社名 詐欺」「商品名 欠陥」などのネガティブなキーワードがサジェストに表示されるケースがあります。
定期的なサジェストのモニタリングを行い、問題のある候補が表示された場合の対策を講じましょう。
サジェストは検索ユーザーの行動パターンに基づいて自動生成されるため、完全に制御することは難しいものの、適切な対策により状況を改善できます。
サジェスト対策の効果
適切なサジェスト対策はブランドイメージを守ることができます。
サジェスト対策では、企業公式サイトのSEO強化や有益なコンテンツ発信により、ポジティブなキーワードの検索頻度を高める取り組みがあります。
自社に関連するポジティブなキーワードを特定し、それらを含むコンテンツを戦略的に発信します。
また、検索エンジンへの削除依頼も効果的です。
サジェスト対策は短期間で結果が出るものではなく、中長期的な取り組みが必要です。
検索エンジンの評価アルゴリズムは常に変化するため、最新の動向を把握しながら対策を継続しましょう。
成功事例
サジェスト対策により状況が改善した実例も多くあります。
実際に「〇〇株式会社 ブラック」「〇〇株式会社 パワハラ」というネガティブなサジェストに悩まされていた会社が、対策したところポジティブな検索候補に変化したという事例がありました。
サジェストにポジティブなワードが表示されれば、会社のイメージが向上します。
専門会社に依頼することで、より高い確率でポジティブワードを上位に表示させることが可能です。
まとめ
本記事では、ネット誹謗中傷に対する初期対応から法的措置、メンタルケアの方法まで解説してきました。
インターネット上の誹謗中傷は企業や個人の評判を一瞬で傷つける深刻な問題です。
事実無根の書き込みやデマの拡散は、匿名性を背景に急速に広がり、長期的な影響を及ぼします。
初期対応の迅速さが重要であり、証拠保全からプラットフォームへの削除依頼、法的措置の検討まで、段階的なアプローチが必要です。
誹謗中傷対策は一時的な対応ではなく、継続的な取り組みが必要です。
デジタル社会において、企業や個人の評判を守るための知識と対策を備えることは、今や必須のリスク管理となっています。